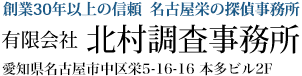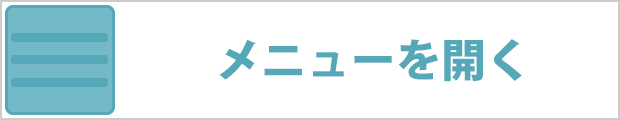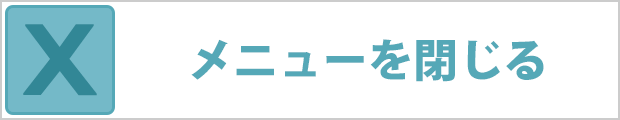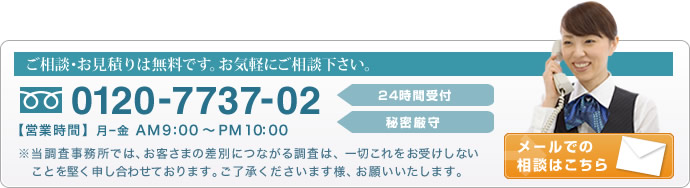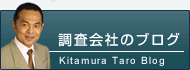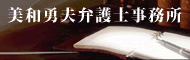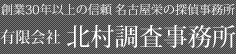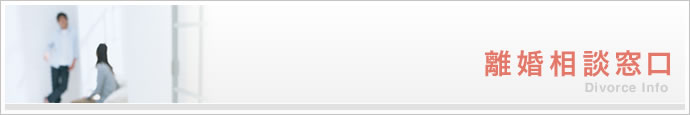
裁判離婚
調停前置主義
民法は第770条で、一定の原因がある場合に限り、協議離婚が成立しない場合には訴訟を起こすことができ、裁判所は理由が認められれば離婚の判決がなし得ることとなっており、これを裁判離婚といいます。
離婚等の家事事件は、性質上訴訟での解決になじみにくい面があり、できる限り話し合いによる解決が望ましいとのことから、家事審判法第18条第1項により調停申立をするよう求められており、調停申立をすることなく訴訟を起こした場合は、裁判所は事件を調停にまわすこととなっています。(家事審判法第18条第2号)
これを調停前置主義といい、離婚だけでなく、家事審判法第9条第1項乙類の事件とされる婚姻費用分担や財産分与、親権者指定等は調停を先にすることが求められています。
ただし、相手方が行方不明で所在地不明となっていることが明白な場合や、一旦調停を申し立て家庭裁判所で話し合われたものの合意できず、申立を取下げ、当初より調停が行われなかったとされるような場合には、調停をなさずとも訴訟の受付がされる場合があります(家事審判法第18条第2項但し書)
手続法の特殊性
1.通常の民事事件(不法行為での損害賠償事件、貸金請求事件等)の訴えについては「民事訴訟法」の規定に従い処理されることとなり、裁判所も請求金額等で簡易裁判所もしくは地方裁判所に振り分けられています。
しかし離婚等の身分関係に関わる訴えは「民事訴訟法」の特別法に当たる「人事訴訟法」の規定に従うこととなっており(同法第2条)同法が平成15年7月16日(施行、平成16年4月1日)全面改正されたことにより訴えを取り扱う裁判所が地方裁判所から家庭裁判所に変更されています。
2.離婚訴訟の場合、人事訴訟法第19条で一部民事訴訟法の規定を排除するため、欠席判決(民事訴訟法第159条)は認められず、相手方が不出席でも証拠調べが必要となります。
また職権で当事者の主張しない事実についても調査したり(人事訴訟法第20条)離婚の訴えと伴に提起した親権者指定や財産分与請求等の付帯請求について、職権で家庭裁判所調査員に調査させたりすることができる(同法第33条)等の特殊な手続きがあります。
平成15年の人事訴訟法の改正に伴ない、従前であれば不可能であった訴訟上の和解、請求認諾等の手続きでも離婚がなし得ることとなっています。(同法第37条)
離婚原因
民法は第770条第1項で、離婚の訴えが起こせる原因としては下記の5つのものに限定しています。
- 不貞 (不貞をおこなった本人が認めるか又は訴え人が立証・証明)
- 悪意の遺棄 (法律義務を怠る・たとえば全く生活費を家庭に入れない等)
- 生死不明が3年間 (管轄の警察署に失踪人の届出、受理)
- 回復の見込みがない極度の精神病 (第三者機関の証明書・医師の診断書等)
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由 (1.~4.と同じく何らかの立証が必要)
そして1.~4.までの原因は5.の例示となっているものと考えられており、同法770条第2項により1.~4.までの原因について事実として認められる場合でも裁判所の裁量で離婚が認められない場合があることには注意が必要です。
そのため裁判では1.~4.までの原因だけを主張し、裁判所がそれを否定した場合、同じ事実関係に基づき5.を原因として別に訴えを起こすことは認められていません。(人事訴訟法第25条第1項) そのために訴訟を起こす場合には1.~4.までの原因の主張だけではなく5.の主張もしておいたほうが良いといった問題もあります。
1.不貞行為 (浮気・不倫・不貞行為全般)
配偶者以外の異性と性交渉を持つことが不貞行為と考えられています。これはあくまでも自由な意思のもとになされることに限られ、強姦や脅迫下における性交渉はあくまで被害者にしかあらずとても不貞行為とはいえません。
事実上の離婚後一定期間経過した後の異性との性交渉は不貞とはならない場合があります。
また特定の異性とだけの性交渉を持つといった必要性はありません。不特定多数と関係を持った場合も当然に問題となり得ます。不貞行為は、訴え提起時まで継続している必要はなく、過去の事実であっても問題となります。
しかし一方の不貞行為が終わり現時点で夫婦としての平穏で問題のない生活に戻りその状態が一定期間継続している場合には、過去の不貞を蒸し返して請求することは認められない場合があります。
また不法行為には他の離婚原因に比べて重大な義務違反と考えられているために、配偶者側の問題のある生活態度等が原因でその不貞行為に至ったような場合でも、不貞行為が認められれば多くは離婚請求が認められます。
そして不貞に関する限りは過去の判例等はともかく、最近では前述の民法第770条第2項により、離婚請求が認められないといった判断はほとんどありません。
2.悪意の遺棄 (家庭生活・夫婦生活等に非協力的な状態)
正当な理由もなく婚姻の基本となる民法第752条の(同居・協力・援助義務)を行わない行為をいいます。例えば下記の行為が、悪意の遺棄にあたります。
- 一方が家を出て残された家族等に生活費等の援助義務を全くせずに、しかるのち相当期間放置状態にしたりしておく等。
- 逆に相手方を家に入れずに放置したり、勝手に家の鍵を変えてしまい相手方を物理的に入室困難な状態の外形を作ること等。
- 更には一方が仕事の関係で転勤した場合に他方に同居を求めても理由もないのに拒む等、相手側に婚姻生活を継続する意思がないと思わせる外形をとること
またこの場合に悪意とは、夫婦共同生活を完全に止めてしまうといった積極的な意思をいいます。ですからそれを裏付けるだけの外形が必要となります。
そのために家を出てしまった期間等も重要となりますが、状況如何では数ヶ月間といった短期間の実績だけでもこれが認められる場合があります。
但しこの原因は評価が難しく微妙なところもあるために、悪意の遺棄の一本だけの主張をするよりは、5.の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一つの状態として、他の問題点と伴に遺棄の事実をあげる方が認められやすい場合があると思われます。
3.生死不明が3年以上
(外形上、行方不明であり所轄の警察署に届出が出してある状態)
生死不明とは単なる行方不明を言うのではありません。生きているのか死んでいるのかを証明できない状態をいいます。残った配偶者や親族等に所在地は教えてなくても、本人から電話があったり又友人知人がどこかで見かけた等の情報があるような場合は全くこれには該当しません。
戦争や震災等の特異な社会状況下以外では、立証等の関係でこれを単独の原因とすることは難しいと思われます「悪意の遺棄」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」を原因として、その一事情として問題とする方が実務にそくした現実的問題提起だと思います。
これを原因として離婚を認める判決が出ても、その後に判決前に相手方が死亡していた事実が判明した場合は、判決があっても離婚は無効となります。
民法第30条では7年以上生死不明の場合、申立により失踪宣告がなされることとなり、その結果、死亡したものとみなされるため、これをもって婚姻関係を終結させることができます。
この場合にも、生存が判明し上記宣告が取り消されると、当然に婚姻関係が復活するために、長期間の生死不明の証明が可能な場合は離婚訴訟を起こすほうが良いと思われます。
4.回復の見込みがない極度の精神病
民法が一方配偶者の精神病を離婚原因の一つにあげているのには、婚姻の本質ともいえる相互協力義務(民法第752条)が充分になし得ないといったことによります。そのために単に一方がうつ病で治療のために通院や入院をしているだけでは認められません。
精神病の症状が重篤で精神面での夫婦としての協力状況が充分に継続維持てきないことが重要になります。
また精神病とは言いがたく「薬物中毒」や「ヒステリー」等の場合は、これを原因としないで程度で判断しなくてはなりませんが、5.の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として申立をするべきでしょう。
精神病を原因とする場合には、相手方は基本的に自活力を失っている場合が多く見受けられます。離婚をすればすぐにも生活に影響が出ることは明白なために、民法第770条第2項を理由に認められないといった事例も見受けられます。
そこで最近では極度の精神病で離婚を認めざる得ない場合も申立をなす配偶者側が相手方の将来の生活や治療にかかる費用等について具体的方法を提示していることを条件に認めていく方向にあります。
(例えでは、一定期間の生活費や治療等にかかる費用の支払いの提示)
しかしこれらの配慮のないままに訴えを起こすと、この原因については前述のように否定される場合が大ですので充分な配慮をもって望むべきでしょう。
5.その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判所において離婚が認められる理由として前述の1.から4.までの原因のほかに、夫婦としての「同居の義務」や「相互協力援助」(民法第752条)を履行できないといった、明らかに夫婦の共同生活を維持継続していくことが困難なまでに破壊されているような場合に認めるとされるのが、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」となります。
ところがこのように夫婦関係が破綻してしまったと判断される基準は、必ずしも明確で画一的なものではありません。
双方の離婚に対する意思や態度、子供の有無やその年齢及び発育状況等、信頼関係の破壊の程度、経済状況、身体状況、性格等一切の事情から総合的に検討し判断されます。
具体的なものとしては、長期の別居、離婚に対する意思の強さ、精神病以外の重大な病気や身体的、精神的障害、または相手方の暴力、虐待(DV)
相手方の家庭を無視した宗教活動行為、性交不能や拒否、勤労意欲の欠如、多額の借金、親族との関係、性格の不一致等々が考えられます。
しかしこれらについて単一のものだけで認められる場合は少なく、特に離婚問題で一番多くあげられる性格の不一致だけでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められることはなく、他の多くの要素と併せて認められるものであると考えておいた方がよいでしょう。
また経済的に弱い側や未成熟の子供ら等に対する配慮から、夫婦関係が破綻していても認められない場合が多くあることにも注意が必要です。
有責配偶者からの離婚請求
民法第770条第1項(離婚原因での、3年間の生死不明・回復の見込みのない極度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由)の規定を見ると、基本的には夫婦関係が破綻した場合は離婚が認められるとの破綻主義認識をとっているように見受けられます。
しかし昭和62年9月2日の最高裁判所判決が出されるまでは、破綻の原因を作った側(不貞・悪意の遺棄・暴力等をなした側)からの離婚請求は、いかに夫婦間が破綻していようとも信義誠実の原則からして認められないとして、請求が認められないこととなっていました。
そのために夫が家を出て、別の女と10年~20年と生活を続けてその間に子供も生まれ、また夫婦間の子供も成人に達して独立した生活を営むようになっているにも関わらず、妻が一切離婚に応じず、そのために非常にいびつな状態のままの生活をおくっているケースがあり、夫が死亡すれば感情面も手伝って相続やその他の問題が著しく難しくなり混乱をおこす事態が見かけられ社会的問題となりました。
ところが昭和62年9月2日の最高裁判所判決により、一定条件下では有責配偶者からの離婚請求も認められることとなり、このようないびつな夫婦関係の解消が一定条件を満たしている場合可能になっています。
そしてこの判決では、離婚が認められる条件としては、長期間に及ぶ別居生活等、外形上からも明らかである夫婦関係の破壊、そして夫婦の間に未成熟の子がいないこと、さらには有責配偶者が残された配偶者に離婚まで、もしくは離婚後も配偶者が生活に困らないよう経済的な援助などで安定した生計が営めるような状況にあること等を求めています。
尚、別居期間は概ね10年以上という考え方がありますが、期間については必ずしも絶対的なものではなく明確な基準はありません。
最近の傾向としては、いびつな状態の夫婦関係を長期間に渡り継続させるよりも、上記の条件(主として離婚後の配偶者の生計の維持)が担保できうるならば、いびつな状態の期間を短くしようとするように思われます。
そして最高裁判所判決後は、実務の面でもこの基準によって処理されていると思われますが、有責配偶者からの離婚請求が全面的に認められた訳ではなく基本的な考えは上記のとおりであり、また上記条件にあてはまる場合のみ認められるものとの考え方が必要であると思われます。